“人”から進める変革
〜現場から語るチェンジマネジメントのリアル〜
変化の時代において、競争力の鍵は単なるテクノロジー導入ではなく「人がどれだけ変化できるか」。世界経済フォーラムの「2020年雇用の未来レポート」では、人的変容こそが未来の企業力の中核になると報告されています。(*)
DX、業務改革、グローバル展開など、企業における変革の波はこれまでになく大きく複雑になっていく中、注目されているのが「チェンジマネジメント」。本連載では、現場で実際に変革支援を行うチェンジマネジメントのコンサルタントたちが、プロジェクトのリアルや苦労、成功の鍵を語ります。全4回を通じて、変革を「人」から進めるとはどういうことか?を探っていきます。
(*) 出典:World Economic Forum, The Future of Jobs Report 2020, https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/
メンバー紹介
今回の座談会に登場するのは、こちらの4名です。

【写真左から】
回答者:和田円香、多田羅勇一、根本佳代子(グローバルコンサルティング事業部プロジェクトマネジメント/チェンジマネジメント コンサルタント)
聞き手:笹岡慎介(チェンジマネジメント エデュケーション サービス セールスリード)
[第1回]チェンジマネジメントとはそもそも何か?その本質と活動の全体像
― 成功の定義から始まる「人」の変革支援とは ―
「プロジェクトを成功させる」とは何か?その問いに立ち返るところから始まる、人の行動変容の支援とは何か。支援の現場に立つコンサルタントたちの実体験と共に、変革支援の第一歩について聞いた。
「チェンジマネジメント」の解釈は各社各様
— 皆さんは、様々な変革プロジェクトにおいてチェンジマネジメントの活動を支援するコンサルタントとして従事されていますが、まず単刀直入にお伺いします。皆さんの言葉で、「チェンジマネジメント」とは何でしょうか?
根本: チェンジマネジメント活動と評されているものの、トレーニングとコミュニケーションだけ、とみなされているケースもよく見るのですが、それだけではないと考えています。「このプロジェクトはどういう状態になれば成功か」から定義して、成功に向かってプロジェクト全体やステークホルダーなどが適切なアクションを起こせるようにする様々なことを、“チェンジマネジメント”として私たちは捉え、取り組ませていただいています。
— それはある特定の人たちだけに向けて支援をするのではなく、プロジェクトに関わる幅広い人全体の支援をされているという理解であっていますか?
根本: はい、その通りです。チェンジマネジメントチームがステークホルダーに直接アプローチする場合もあれば、経営・シニアマネジメント層や、社員にとってのスーパーバイザーとなる中間層にアプローチし、間接的にステークホルダー全体に展開する場合もあります。特に、経営・シニアマネジメント層の協力とリーダーシップの発揮をサポートすることが、チェンジマネジメント活動をするうえで非常に重要です。
最初に行うことは「成功の姿」の確認
— お客様側のチェンジマネジメントをリードされている方がよく悩まれていることや、その方々から受ける相談はどのようなものがありますか?
多田羅: プロジェクトを始める前は、“何から始めたら良いかわからない”、“どう相談したら良いかわからない”、といった悩みを伺うことがよくあります。また始めてからは、“具体的に巻き込みたいマネジメントからの協力が得づらい”、もしくは“どうしたら組織に情報を効果的に伝えられるか”といった相談があるように感じています。
— お客様から受ける相談は、プロジェクトの段階やフェーズごとで異なると理解しましたが、最初の何から始めていいかわからない場合はどのようなご支援からされるのですか?
多田羅: 関係者が、“チェンジマネジメントとは何をしてくれるものなのか?”と疑問を持ちながらプロジェクトが始まることもあります。そのような時は、「チェンジマネジメントとはどのような考え方で、何を目標にどういったことをする取り組みなのか」という、チェンジマネジメントチームがやろうとしていることを丁寧に説明し、理解していただくところから始めます。ここを疎かにするとその後の具体的な内容が全く入ってこなくなってしまうので、当たり前ですが意外に重要なポイントです。
その後、プロジェクト立ち上げ時では、”このプロジェクトは何を目指しているか?”といった、プロジェクトの動機に立ち返りながらのゴールや目標の再確認は必ず行います。
これまで多くのチェンジマネジメントプロジェクトを支援してきた経験上、誰かが作ったプロジェクトのゴールや目標は存在していても、曖昧な表現が用いられ、漠然としていて具体化されていないことも意外と多いです。また、プロジェクト関係者の誰もが同じ理解ができるような表現になっていないことも多いです。マネジメント層や管理職層など、一部の人は理解しやすいものの、組織全体で同じ目標をイメージできるか?同じゴールを想像できるか?というと、そのようになっていないケースも多く、改めて整理して言語化するところは大切なステップになります。
和田: 日本国内における変革は、つい最近まで、制度やプロセス、システムやツールを作ることがゴールだと感じるプロジェクトが多くありました。が、昨今はソリューションが日進月歩で進化しており、それらを導入したその先にある自らの姿がわかりにくい状態になっていると感じます。例えばDXを推進した先に得られるデータをどう活用することでどのようなベネフィットを享受したいかといった成功の姿について、ある程度具体的な共通理解がないまま進めていくと、ゴールが見えなくなるということが起きるのではないでしょうか。どこに到達したらゴールなのかが分からない場合、変革の管理も本質的にはできないということになりますので、まずそこをクリアにしようという動きが最初に発生します。
— そうすると、プロジェクトの開始前や開始初期段階で、その変革をなぜ行うのか、どういう段階でどうなっていたいのかについてしっかり定義をするところから始めるという理解で正しいでしょうか。
和田: “成功の定義”については、プロジェクトが始まる前にプロジェクトを立ち上げたリーダーやそれを補佐するチームが議論を重ねてきているものだと思いますが、様々な視点から質問することで、これを具体化、明確化、聞き手の立場で言語化する部分については、チェンジマネジメントが関与する初期の重要なステップであると考えています。
— その言語化されたものを、PMやマネジメントだけではなく、もっと幅広い様々な方を巻き込んで共通理解を促していくわけですね。
和田: その通りです。例えばお2人は、この辺りに特に重きを置いたプロジェクトに参画されていると思いますが、何かエピソードを紹介いただけますか?

次回は、「総論賛成・各論反対の壁の乗り越え方」に迫ります。
[第2回]チェンジマネジメントを適用する際に気を付けていることは
― 総論賛成・各論反対の壁の乗り越え方 ―
プロジェクトの方向性には賛成しても、実際の業務変更には抵抗がある。そんな「総論賛成・各論反対」に直面したとき、チェンジマネジメントは何ができるのか?現場への丁寧な伝え方、巻き込み方、そして共感を生むメッセージの作り方について聞いた。
“成功”を定義することの必然

根本: 例えば、システム導入の際に、掲げられている目的はあるものの、システム導入目線で考えられているため、導入すること自体が目的となって、その後の世界はあまり語られてなかったりすることも現実にはあるかと思います。ただ、経営・シニアマネジメント層の皆さまご自身のなかに、システム導入後の目指したい姿やビジョンをお持ちである場合もあります。私がご支援したケースでは、経営・シニアマネジメント層の方々に「システム導入後の目指したい姿やビジョン」をヒアリングさせていただきました 。
また、変革が複数の部門にまたがっているケースにおいては、それぞれの部門長の目指したい姿が違っていることもあるので、各部門の目指す姿として伺ったものを取りまとめ、最後に全体で認識合わせをするというアプローチを取りました。
これにより、会社全体が目指したい姿や考えを知ると同時に、各リーダーが部門レベルで目指している姿や考えも導き出すことができ、双方のすり合わせを行うことができました。
— ご紹介頂いた活動の結果、反応はいかがでしたか?
根本: はい、やっておいてよかったというご意見をいただきました。経営・シニアマネジメント層のヒアリングを通して、「このシステムを導入する理由がやっと分かりました」という感想もいただきました。システム導入の成果として到達したい組織の姿って、意外と言語化されていないんですよ。なのに、そのままプロジェクトが進んでしまっているということも多い。ちなみに、目指す姿が言語化できたら、主要な説明会などの冒頭で常に掲げ続けます。社員の皆さんも同じ目的を目でみて、確認できるようにします。より浸透しやすくするため、メッセージをわかりやすくキャッチコピー化することもありますね。説明会に出席した社員の方々からは「システム導入の目的が理解できた」「会社の目指しているものが分かった」などのフィードバックをいただきました。
「総論賛成・各論反対」
— では、この次の段階ですが、実際にプロジェクトを推進する際に、どのような支援をされていますか?
和田: 「総論賛成・各論反対」という言葉はプロジェクトを推進している際によく耳にする言葉ですが、これはある意味当然のことと考えています。プロジェクトが掲げている将来の組織の方向性や方針には賛成するものの、各個人には仕事に対する思いがあり、最もやり慣れたやり方で最大限のパフォーマンスを発揮し、掲げた目標を達成しようと日々努力しています。このような個人の思いや内部・外部環境要因により、物事がスムーズに進まないことは往々にしてあることかもしれません。
— 総論賛成は、比較的シニア層での共通理解である一方、現場に浸透させて行くフェーズでは各論反対、いわゆる抵抗のようなことが出てくるということですね。
多田羅: 多くの場合、マネジメントが“この会社は先々どうあるべきか“という視点から将来の姿を定め、その姿を実現するための取り組みとしてプロジェクトが発足します。
経営や変革に近い社員は、自分の役割や考えとプロジェクトの方向性がある程度リンクしやすく、言語化されたプロジェクトの目的などは理解しやすいものです。
一方、日々業務を行う社員にとっての仕事は、「決められた期間内に決められた作業量をこなすこと」や「チェックして、おかしなことになっていないことをしっかり担保する」など、作業効率や品質保持を重視するような作業が中心となることも少なく
ありません。もちろん、それらの業務を積み重ねた先は会社が目指す将来に繋がっていて、広い意味では方向性は同じだと言えます。
しかし、役割や考え方、担当している業務内容が異なる社員に向けて、同じ言葉と表現で目的を共有しても、それが響かない人たちは出てきます。人によっては、「このプロジェクトを進めることが、いまの自分の作業負荷を少しでも軽くしてくれるのか?」といった目線で捉えるわけで、そういった社員にとってはマネジメントが発する”プロジェクトの目的“は、なかなかピンと来ません。
同じ内容を伝えても、立場によって見え方や受け取り方が違うため、目的がなかなか浸透しないという事が起きてしまいます。

「総論賛成・各論反対」を乗り越える
多田羅: 目的を浸透させるためには、どのような伝え方をすると理解しやすく協力してもらいやすくなるのかを意識することが大切だと思います。これを聞くと当たり前のように思えますが、実際の現場においては伝え方をあまり意識できていなかったり、今までのやり方と同じようにやればいいや、と進めてしまっていたりすることも多いです。
例えば、「プロジェクトオーナーがキックオフの時に喋ってくれたから、みんな理解してくれただろう」「共有サーバにプロジェクトの目的が書かれた資料を格納したことを一斉メールでフォローしたから大丈夫だろう」といった場面があるとします。
本当にその伝え方で全員に理解してもらえるか、対象者によってはもう少し分かりやすい表現に変更した方が良いのではないか、フォローアップの仕方は他にもあるのではないか、などを考慮することも多いです。
この段階を丁寧に行うことは社員の抵抗を軽くすることにもなり、結果として各論反対を緩和する要素の一つとなると考えています。
根本: 「各論反対」の別の例ですが、“何が変わるのか”、また“何が変わらないのか”が分からないことによって、不安が生じたり、成功に貢献したい気持ちが薄れたり、嫌だなと感じる人もいると思います。そのため、何が変わって何が変わらないかという情報は、意識して丁寧に伝えます。こういった情報を出すと同時に質問が増えることもあります。例えば、私がご支援したプロジェクトのチェンジマネジメントチームでは、全ての質問に一つ一つ答える仕組みを作り、実践していました。あくまで、一つの実践例にはなりますが、各論反対的な要素が燻っている“種”のようなものを見逃さずに、しっかりと向き合うコミュニケーションも、重要なポイントの1つかと思います。
「変化するのは組織ではない、人である」
和田: 究極的に言うとまずは、「人」を見つめることだと思っています。Prosciのチェンジマネジメントが大事にしている概念、マントラの1つに「変化するのは組織ではない、人である」というものがあります。一見反対しているように見える人も本当はそうではない場合もあると思います。
そこで、なるべく科学的かつ具体的なデータに基づいて、アンケート等を活用し、一人一人の懸念や期待等を確認します。また、調査して終わりではなく、数値データや反応等を具体的に分析して、それぞれのグループや人に応じたアクションを取る、またその結果を確認する、というPDCA(計画・実行・振り返り・改善)を継続します。
また、この調査・分析内容や、そこからの示唆を受けたアクション項目を、いかにプロジェクトマネージャーやリーダーレベルが重視・注目し、一緒に解決に向けて動いて頂けるかも効果に大きな影響を与えると考えています。
— 同じ一つのプロジェクトでも、利害が複雑だったり、多岐にわたっていたり、それが部署によって違うとか、ポジションによって違うといった複雑な状況を、なるべく全員が理解して、必要性を感じてもらえるような管理手法というのがProsciのチェンジマネジメントということですね。

次回は、「変革時の抵抗」に迫ります。
[第3回]変革時の抵抗に備える
― Prosciに基づく“先回り”の変革管理 ―
変革時の抵抗は避けられない―。そう思い込んでいないだろうか?チェンジマネジメントの方法論には、実は“予防”という視点がある。人の反応を予測し、リスクをあらかじめ特定する。そのためのフレームワークと実践例を聞いた。
抵抗を予測・分析する
多田羅: チェンジマネジメントの本質的な考え方は、予防だと思っています。起きてから対処するのではなく、「発生しそうな事象を予測し、それが起きないように、または起きても影響をできるだけ小さくできるようにどのような手を事前に打っておけるか」を考えることを繰り返すイメージです。
変革中に起きる抵抗の話であれば、どのようなケースで抵抗が起きうるのか、過去に起きた抵抗の傾向などをあらかじめ調べて分析します。
そうならないようにするには、もしくはそういう人たちがあまり多くならないようにするにはどうしたらいいかについて、あらかじめ策を考えて実行する。実際にはそれでも抵抗と呼ばれるものは起きますし、その際は事後対応が必要となります。ですが、もし事前の予防策を十分にとらなかったら、もっと大きいものになっていると思います。

— 予防しておくべき事柄を、事前に想定して特定しておくということもProsciのチェンジマネジメントの理論にあるのでしょうか?それとも、そこはコンサルタントの経験があればこそですか?
多田羅: これは実際にProsciの方法論の中にプロセスとして組み込まれています。この変革はどういったタイプのものだから、どういうところに影響が強く出そうか、どこにリスクがありそうか、など様々な観点で予防のための分析を行います。
— 一連の活動について、クライアントの皆様からは何をやったらいいかわからない、というお悩みを聞く事はありますか?
多田羅: 比較的多くありますね。私たちはチェンジマネジメントサービスを提供するときにProsciの方法論を使っているのですが、お客様側も同じように方法論を理解していないと難しいところは正直あると思います。どのようなことをやるのか全く知らない状態で、我々がサービスを始めても、どうしても分かりづらいですよね。
Prosciの方法論を学ぶ方法もサービスの1つとして提供していますが、あくまでも教科書を読んで中身を理解する形です。実際のプロジェクトに適用して進めるのは、そう簡単ではありません。私たちも多くのプロジェクトを経験していますが、それでも悩むことは多いです。

和田: 私もプロジェクトをやっていて実感するのは、特に大規模プロジェクトや海外のチェンジマネジメント担当の方々と英語での議論が必要な状況において、共通言語、すなわち同じ概念と同じやり方で議論ができるということは、何倍も仕事を早めると思っています。ただでさえ「人」という、ふわっとした対象の移行を支え、リードしようとする活動ですので、言葉や概念があっていることで本題の議論に時間をかけることができます。こういったことができると大変感動しますね。
多田羅: 共通言語がないと、正直かなり厳しいですね。

変革における“抵抗”は、必ずしも避けられないもの。だからこそ、事前に想定し、備えることが重要です。
その上で、次に求められるのは、人を動かす力─「変革を前進させるための推進力」。
最終回となる次回は、いよいよ、「人の変革、成功の鍵」に迫ります。
[第4回]「人」の移行における成功の鍵は何か?
― スポンサーシップと“人への想像力”が変革を動かす ―
どんなに優れたシステムや戦略があっても、人が動かなければ変革は進まない。では、その“人”を動かすには何が必要か?チェンジマネジメントを成功に導くための本質的な成功のための鍵について、最前線の実践者に聞いた。
変革成功の鍵は何か?──登壇者に聞く「最も大切な要素」
— ここまで、チェンジマネジメントとは何か、またどのような活動を行うのか、そして「総論賛成・各論反対」や抵抗への対処方法について議論をしてきました。ここで改めてお伺いします。
皆さんが様々な変革プロジェクトでチェンジマネジメントのご支援を推進していく中で、何が一番大事だと思いますか?
リーダーシップと現場の馬力が不可欠
― 根本の視点:スポンサーの役割と現場チームの重要性

根本: 私は二つ挙げたいと思います。一つ目はProsciの用語で言う「プライマリースポンサー」や「スポンサー」、つまり、“プロジェクト最高責任者やシニアマネジメント層のリーダーシップ”。そして二つ目は、お客様と私たちコンサルタントで構成されるチェンジマネジメントチームがいかに現場レベルで“泥臭く馬力を出せるか”。この二つが絶対必要だと思っています。
一つ目に関して言うと、多くの場合、社員の皆さんは「なぜ、今、このプロジェクトをやるのか」という話をきちんと聞きたい。きれいな言葉で語られて耳障りがいいものよりも、スポンサー自身から発せられる言葉を聞きたがっているということは、私がご支援したプロジェクトで実施した社員向けアンケートの結果からも明白です。 例えば、説明会などにおいてスポンサーが自らの言葉で変革を語った後の回答には「リーダーの本気度を感じました。やる気を持ちました。」といったフィードバックが多く見られました。やはり、スポンサーシップやスポンサーの語る言葉や示すビジョンが非常に必要だと感じます。
また、スポンサーとチェンジマネジメントチームの距離感が遠いとうまくいきづらいです。チェンジマネジメントチームが考えた戦略や、スポンサーの協力のもとで実施したい施策があっても、スポンサーとの距離感があったり、何らかのハードルがあったりすると、スポンサーの協力を得るのは厳しいから…と活動が小さくなっていってしまう。そうなると、プライマリースポンサーやスポンサーのリーダーシップが十分に発揮されず、チェンジマネジメントの効果が薄れてしまいます。スポンサーとの関係性が薄いことはチェンジマネジメントの推進が不可能とは言わないまでも、活動を難しくする1つの要素だと感じます。
こういった観点からも、チェンジマネジメントチームを立ち上げる際のメンバー構成は重要です。私たちは外部のコンサルタントとして、最大限のご支援に努めています。しかしながら、外部だからこそ踏み込める範囲には限界があり、特に社内における対人コミュニケーションなどは、お客様ご自身に積極的に関与いただくことが不可欠です。例えば、社内を奔走し、キーパーソンと膝を突き合わせて丁寧に対話を重ねる――そうした地道な関わりに時間と労力を惜しまず、「やりたい」「やれる」と思えるチェンジマネジメントリードや現場のメンバーが存在するかどうか。それこそが、変革成功の鍵であると実感しています。
熱意と信念が推進力になる
― 多田羅の視点:情熱が周囲を巻き込む力に
多田羅: 私が重要だと考える要素は“情熱”と“信じる心”だと思います。精神論みたいに聞こえてしまうかもしれませんね(笑) 情熱はどちらかというとお客様側に必要だと思っています。プロジェクトやその先に目指すものに対して、本気で取り組んでいるんだということが見え始めると、周囲の人を巻き込みやすくなるので。
例えば、プライマリースポンサーがプロジェクトに最も貢献できる活動は、目に見える形で参画することであるとProsciは言っています。ただ、目に見える形と言っても表に出てくればそれで良いというわけでもないんですよね。プライマリースポンサーはメッセージを伝える役割が多いですが、動画やオンライン会議でメッセージを発する際に台本は用意しつつも、しっかりとご自身の言葉で語り掛けて話すスタイルの方が各段に響きます。
多少噛んだり間違ったとしても、自分の言葉でないとメッセージに熱量が乗らないと思うんです。そういった意味で、「情熱」はとても重要な要素だと感じています。
一方、チェンジマネジメントを推進する側は、“チェンジマネジメント”というものと、“その効力”を一旦最後まで信じ抜いて進めることが重要だと思っています。多くの場合、最初は「このチェンジマネジメントって素晴らしいものなんでしょう?」とポジティブなイメージを持っていただけますが、何らかの理由で急に活動に疑問を持ったりする場合もあります。すると途端に勢いを失い、さらに懐疑的な意見が出始めたりすることで、それまでに時間をかけて築いてきたものを大きく失うこともあります。
そもそもチェンジマネジメントは効果をすぐに創出することは困難という性質がありますので、最後までやりきる状態を作らないと、得られるものも得られないというのは、やってきた中で感じる所です。
PMとCMの協働がプロジェクトを強くする
― 和田の視点:信頼に基づく連携と柔軟な運用

和田: 私もスポンサーシップは一つの要だと思います。プロジェクトオーナー、もしくは場合によっては組織統括のお立場の皆様が、変革の必要性を“語るのみ”ではなく、「自分の業績に関わる変化である」という姿勢で“参加”されている場合、プロジェクトは引き締まり、多くの社員が賛同する可能性が高いという結果を何度も拝見しました。
次いで最近特に思うことは、プロジェクトマネジメントとチェンジマネジメントがうまく融合しながら変革を進めることの重要性です。
現場で実践する時には、プロジェクトマネージャー(PM)がビジネス部門の社員の成功をプロジェクトのスコープの1つと捉え、そのための活動をチェンジマネジメントチーム(CM)に任せつつ、パートナーシップを組んで進めていくという姿勢や心づもりがあると、大変効率的に変革プロジェクトは進みます。そのためにはPM/CM間の信頼関係が重要になります。またチェンジマネジメントの活動も、勿論弊社が提供しているチェンジマネジメント資格認定プログラムにて学んで頂けるような、明確なタスクやスコープ、成果物があるものの、状況に応じて柔軟に勘所や力点を変えながら進めるという考え方が、非常に重要なポイントだと思います。
チェンジマネジメント、まずはここから
— では最後の質問です。チェンジマネジメントに関心がある読者の皆様に、まず何から始めるといいか一言ずつお願いします。
多田羅: 今これを読んでくださっているということは、弊社のホームページにたどり着いてくださっているということですよね。リソースやコラムにも色々な情報がありますので、まずはそれらを読んでいただくのが良いと思います!そもそもチェンジマネジメントってどういうものか、またそれを進めるにあたっての考え方といった重要な話は、それらの記事の中でも分かるようにまとまっています。まずは知識を増やし理解を深めるところから始めていただき、それでも困ったことがありましたら、ご遠慮なく我々のところに連絡をいただけると嬉しいです。
根本: ぼんやりとチェンジマネジメントがわかってきたところで、是非やっていただきたいなと思うのは、過去ご自身が関わられたプロジェクトや取り組みを想像しながら、「もし、あの時チェンジマネジメントがあったら…」を想像してみてほしいです。チェンジマネジメントを取り入れずに進めた実際のご自身の経験と、チェンジマネジメントを取り入れてみた場合の可能性を比較していただくだけでも、必要性を実感していただけるのではと思います。私自身、自分がチェンジマネジメントを十分に知らなかった頃に、「あのプロジェクトにチェンジマネジメントを入れていれば、もうちょっと違った結果があったのではないか。もっとうまく皆さんの協力や賛同を得られたかもしれない。もっとプロジェクトがスムーズに進行して、もっと効果的に成果を達成できたかもしれない。」という感覚がありました。こういった想像から「実際にチェンジマネジメントをやってみたい」という気持ちが高まっていった気がします。
— 確かに過去の経験で、「なんでこんなことをやらなくてはいけないのか」などと言われた経験があったら、想像しやすいですよね。チェンジマネジメントがあったら、こういう声を逆の声に変えられた、など。
私たちも最初は手探りだった
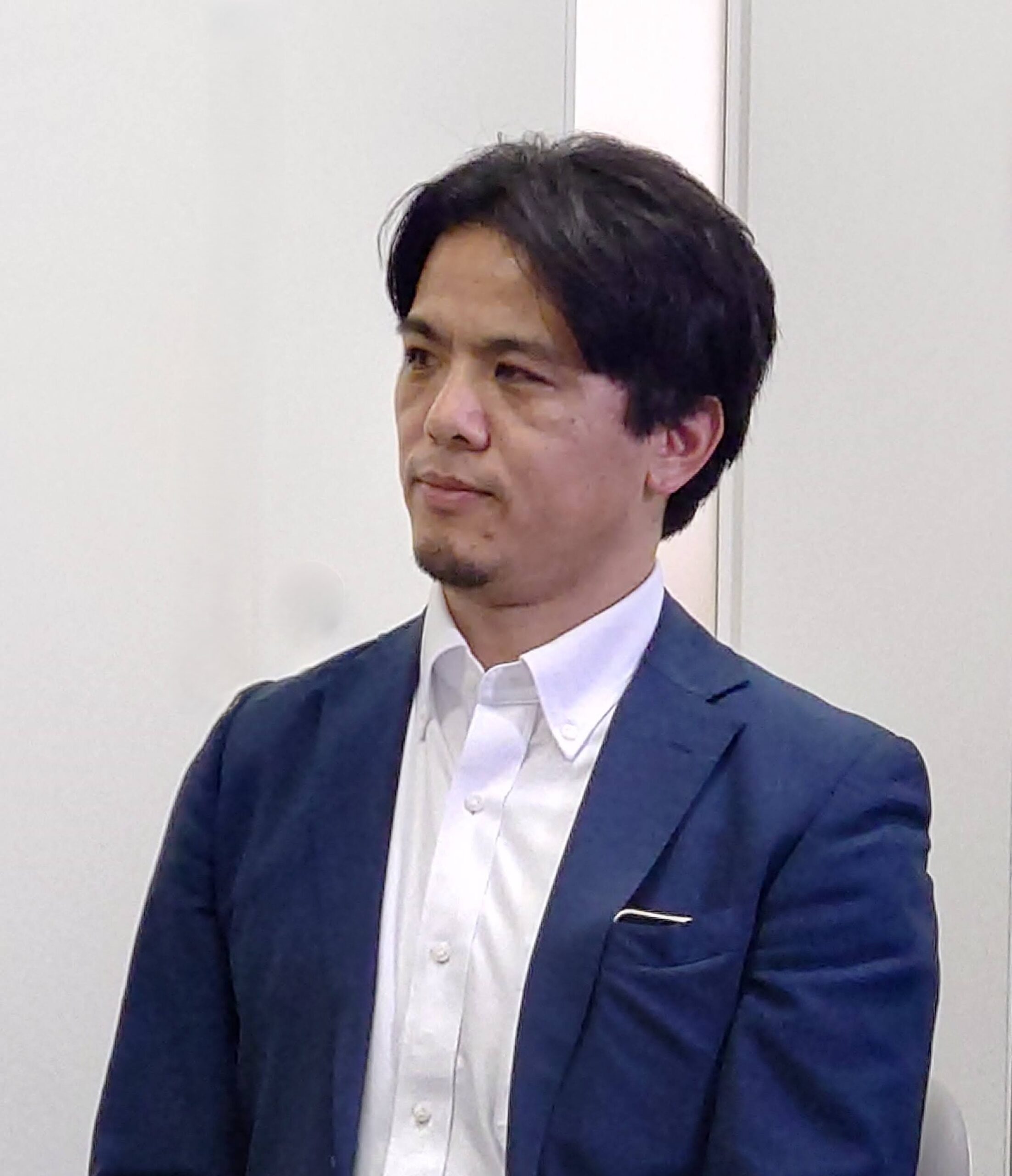
和田: 私も2000年代よりチェンジマネジメントの推進を目指してきましたが、当時はうまく説明するための手立てを持っていませんでした。難しいもの、逆にコミュニケーションや、トレーニングするだけといった印象もありました。そこで、より世界中に分かりやすくチェンジマネジメントを説明できるツールはないものかと探していた所、世界100カ国以上で導入されFortune100企業の80%とビジネス関係をもつProsciに出会いました。世界ではチェンジマネジメントが実際に数多くの人的側面での変革成功実績を創出していることを知り、「人」ができることとチェンジマネジメントの可能性について更に自信を持つに至りました。
お陰様でチェンジマネジメントの理解は各段にしやすくなりましたが、とはいえ実行することは今でも簡単とは思いません。それだけ、多くの人を同じ方向に促し目標を達成することはやはり難しいのだと思います。が、せめてそこに体系的な方法、フレームワークやTipsがあることは大きな心のよりどころになると思います。弊社は無料セミナーなども都度実施していますので、まずはProsciの考え方に触れて頂き、そこからの知識習得、および実践については、ぜひ皆さまと共に研鑽を積んでまいりたいと思っております!
— ありがとうございます。では、質問は以上となります。ありがとうございました!
迷ったら、声をかけてください
読者の皆さま、4回にわたる連載をご覧いただき、誠にありがとうございました。
本対談を通じて、「チェンジマネジメントとは何か」、そして私たちがどのような思いでご支援に取り組んでいるのかを、少しでも感じ取っていただけたのではないかと思います。変革には、迷いや不安がつきものです。だからこそ、私たちチェンジマネジメントコンサルタントは、皆さまの伴走者として存在しています。
「どこから始めればいいかわからない」「このまま進めてよいのか不安」といったお気持ちがあれば、どうぞ遠慮なくご相談ください。
チェンジマネジメントの力を活かし、貴社の“なりたい姿”に向かって、一歩ずつ前へ。
私たちアタウェイが、その一歩を共に支えてまいります。

【無料】チェンジマネジメントの基礎知識
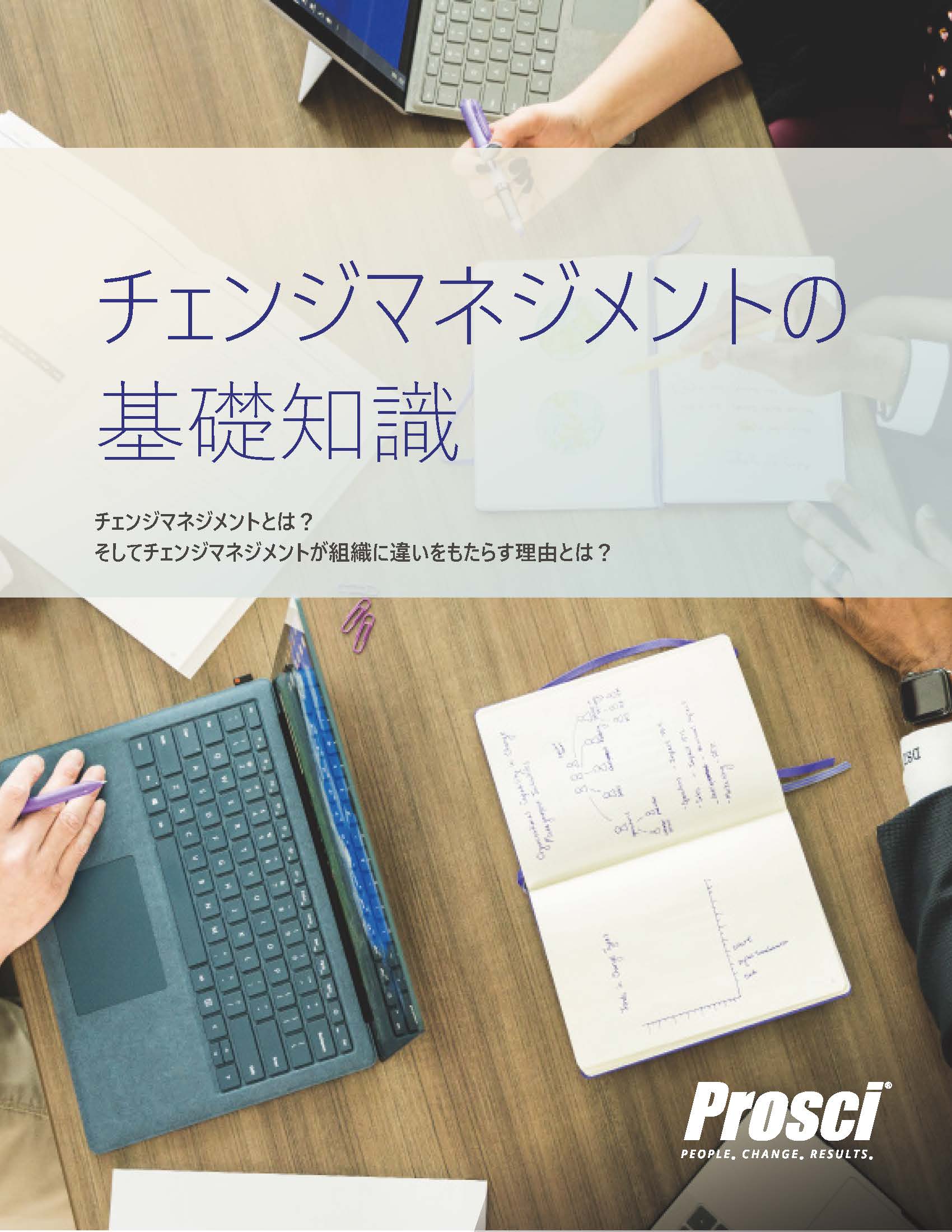
スケジュールや予算を守り、仕組みや環境もしっかり準備できているにもかかわらず、当初の 期待とはほど遠い結果になってしまう変革案件が後を絶ちません。目指してきた姿と結果に ずれが生じてしまうのはなぜでしょう。変革の過程で生まれる新しい考えや求められる動きを 一人ひとりの社員が適切に受け入れ、その中で自身がどうすべきかを理解し実践できること。 それこそが変革本来の姿であり、チェンジマネジメントを行う理由でもあります。











